
更年期障害なんていらない^^
毎日すっきり元気で過ごしたいですよね。
50代ともなると、どうしても更年期障害が出てきてしまいます。
あちこちの不調は辛いもの、今回は「更年期をうまく乗り切る方法」について、まとめました。
女性の50代が更年期をうまく乗り切る7つの方法とは?
食事で不足しがちな栄養を補いましょう
 大豆に多く含まれているイソフラボンは、骨量を増やしたり、コレステロール値の上昇を抑える作用もあるので、更年期の女性には欠かせない食品です。
大豆に多く含まれているイソフラボンは、骨量を増やしたり、コレステロール値の上昇を抑える作用もあるので、更年期の女性には欠かせない食品です。
大豆の煮豆や納豆、豆腐、おからなどの大豆食品を積極的にとりましょう。
骨粗しょう症の予防には、カルシウムとその吸収を助けるビタミンDとKも一緒にとると効果的です。
適度な運動をしましょう
 更年期を乗り切るのに運動はとても効果的です。それに更年期障害になると骨粗しょう症になりやすくなります。
更年期を乗り切るのに運動はとても効果的です。それに更年期障害になると骨粗しょう症になりやすくなります。
運動は、血行が良くなり、肩こりやひざの痛み、便秘や動悸、息切れなどの症状の改善になります。
それに、抑うつ気分や不安など心理面への効果も大です。
ウォーキングや水泳などの有酸素運動は、呼吸を深くし血液循環もよくするので、楽しみながら続けられる運動を選びましょう。
ストレスを避けゆったりしましょう
 更年期障害になるとだるさ、倦怠感、疲れなどが出てきます。
更年期障害になるとだるさ、倦怠感、疲れなどが出てきます。
今までできていた家事などができなくなったり、少し動いただけで体がだるくなってしまい休憩を頻繁に取らなくてはいけないような状態になる人もいるそうです。
そういう精神状態の時にストレスを溜めてしまうとどんどんと悪化してしまいます。
ストレスを全くなくすということは難しいことかもしれませんが、なるべくストレスを溜めないようにし発散方法を見つけることが大切です。
タバコ・アルコール・カフェインを避けましょう。
 タバコを吸う女性は、吸わない女性よりも更年期症状がずっと早く現れる可能性があります。
タバコを吸う女性は、吸わない女性よりも更年期症状がずっと早く現れる可能性があります。
十分な睡眠をとりましょう
 睡眠不足は症状を重くします。
睡眠不足は症状を重くします。
体がほてって寝つきが悪い人は、
氷枕などを利用すると寝つきがよくなる場合があります。
薬物療法【ホルモン補充療法】
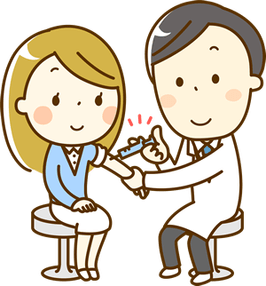 不足しているエストロゲンなどの女性ホルモンを少し補うことで症状を緩和します。
不足しているエストロゲンなどの女性ホルモンを少し補うことで症状を緩和します。
補充療法を5年以上続けると、乳がんが発生する可能性が高まりますが、
5年未満ならその問題はないと考えられています。
薬物療法【漢方薬】
 症状の緩和に、
症状の緩和に、
漢方薬の当帰芍薬散[とうきしゃくやくさん]
加味逍遙散[かみしょうようさん]
桂枝茯苓丸[けいしぶくりょうがん]を使うことがあります。
薬物療法【抗うつ薬や抗不安薬、睡眠薬】
 うつや不安症状が強い場合などには、抗うつ薬や抗不安薬、睡眠薬を使うこともあります。
うつや不安症状が強い場合などには、抗うつ薬や抗不安薬、睡眠薬を使うこともあります。
抗うつ薬には、のぼせや発汗などの軽減を期待できるものもあります。
更年期障害が重いのは、体内でエクオールが作られていないかも?
もしかしたら体内でエクオールが作られていないかもしれないです。
私はあまりにも不調すぎて調べていて「エクオール」のことを知りました。
体内で作られる人と作られない人がいて、エクオールが作れない人ほど、更年期症状は重いという調査結果もあるんですね。
私もビビッて、即検査してみました。
4,000円ぐらいかかるけど、自分の状態を知っておいたほうがいいし、もしこのエクオールが不足していて更年期障害が重いとしたら、補充してあげればいいことですもんね!
それで、体調が良くなったら全然いいじゃないですか!
検査はちょっとめんどくさかったけど、友人に進めて感想を聞いたら、「尿を採るだけだから簡単だった」と言ってました。
私は、超めんどくさがりなので、めんどくさいと思ってしまいましたが、個人差があるんですね~(笑)
一度は検査しておくといいですよ。
検査の流れを詳しく写真入りで説明しているので参考にしてくださいね^^
→ エクオール作れる人とは?見た目でわかる?ソイチェックを受けてみた♪
実は、検査で「作られている」と出ている人でも、毎日適量が作られているとも限らないので、正常値だった人も「エクエル」は飲んだほうがいいんですって。
私は、検査の結果、「作られている」だったけど、体調がすぐれなかったので飲んでます。それが聞いているのかずいぶん楽になりました。
購入するときは、パウチとボトルがあるのでパウチをおすすめします。
→ エクエルのパウチとボトルの違いは?成分、内容量に差があるの?
エクセルのパウチはこちらがお得です!
【まとめ】女性50代がうまく乗り切る7つの対策
更年期の症状は、さまざまで200種類以上もあるといわれています。
症状の重さも人によって違いますし、始まる時期も終わる時期も個人が大きいです。また、いくつかの症状が重なって現れることもあります。
からだに異常がないのに自覚症状が現れる「不定愁訴(ふていしゅうそ)」というものがあり、更年期症状の特徴です。上の7つのポイントを参考に乗り切っていきましょう!
もし、よろしければ、
その前の記事も読んでいただけると参考になると思います。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16afe8f8.406cb642.16afe8f9.14a65fd1/?me_id=1311652&item_id=10000777&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshimin2%2Fcabinet%2Fshohin_otsuka%2Feql-lmtd%2Feql01-lmtd_prc.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshimin2%2Fcabinet%2Fshohin_otsuka%2Feql-lmtd%2Feql01-lmtd_prc.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
